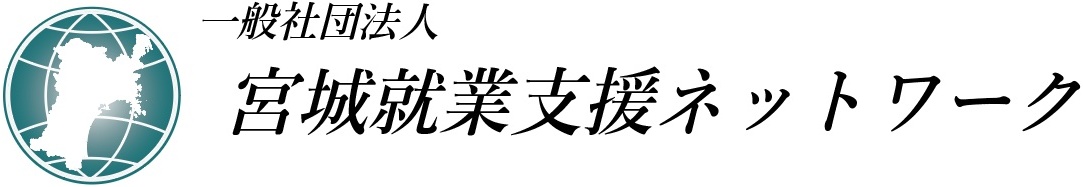宮就ネットが
めざすもの
宮就ネットは、企業と支援機関のプラットホーム作り、自立支援協議会就労部会の未設置地域での設置促進、既に設置されている地域への活動強化の働きかけ、地域状況の分析、全国的な情報を踏まえた障害者雇用・就業支援に係る研修などを通じ、宮城県内の障害者雇用・就業支援のネットワークを構築し、障害者の雇用の促進と安定及び就業支援の質の向上をめざして活動します。
また、活動に際しては、以下の点を大切にしたいと考えています。
〇障害者雇用を通じて誰もが働きやすい職場作りを
障害のある人を職場に受け入れる際には、「仕事を見える化・簡素化・効率化する」「根気よく分かりやすい指導をする」「適切な指示をタイミングよく出す」「頭ごなしの叱責ではなく有用な助言を行う」「成功体験を積ませ達成感を持たせる」「職場の人間関係を和やかにする」「同じ職場の仲間として迎え入れる」「悩み事を親身になって聞く」といったことが望まれます。
もっとも、このような対応は障害のある人だけでなく、就職したての職場に慣れない従業員などにとって望まれるものです。短時間労働のような本人の状況に合わせた労働時間の設定も、子育て中の従業員などにも求められるもので、障害のある人特有の問題ではありません。障害者雇用率を達成するためだけの障害者雇用ではなく、障害者雇用を通じて誰にとっても働きやすい職場作りに取組むことが望まれます。
国連の専門機関であるILO(国際労働機関)は、国際労働基準の制定を通して世界の労働者の労働条件と生活水準の改善を目的として活動していますが、このILOではディーセント・ワーク(Decent Work)の推進を掲げています。ディーセント・ワークは「働きがいのある人間らしい仕事」と訳され、人々が働きながら生活する際に抱く願い(働く機会があり、持続可能な生計に足る収入が得られること。労働三権などの働く上での権利が確保され、職場で発言が行いやすく、それが認められること。家庭生活と職業生活が両立でき、安全な職場環境や雇用保険、医療・年金制度などのセーフティーネットが確保され、自己の鍛錬もできること。公正な扱い、男女平等な扱いを受けること。)が集大成されたものとされています。
これらの願いが十分に実現されていないからこそディーセント・ワークの推進が提唱されているのですが、宮就ネットでは、このディーセント・ワークの視点も踏まえて、障害者雇用を通じた誰もが働きやすい職場作りを意識した活動に取組みたいと考えています。
〇地域ネットワークの形成
障害者雇用の経験に乏しい企業が「障害者雇用を通じて誰にとっても働きやすい職場作りをして下さい」と言われて、そのような取組みがすぐにできるようであれば多くの支援機関や支援制度は不要でしょう。
そのような取組みが難しいから、支援機関や制度があるわけですし、支援機関には、企業がどのように障害者雇用に取組めば良いか分かりやすく説明する能力と、「仕事の見える化・簡素化・効率化」などを進めるための具体的なスキルが求められていると言えます。
また、いくら「誰にとっても働きやすい職場」と言っても、仕事内容や職場環境はさまざまです。障害の有無に関わらず、その人の希望や向き不向き、職場環境との相性を無視するわけにはいきません。障害のある人の興味関心・経験・特徴と、企業のニーズと現状の双方をしっかり把握し、障害のある人と企業が出会えるように支援することも必要です。
職業に関する興味関心がはっきりしない人に対しては、さまざまな情報や体験を提供することでその人のニーズ形成を支援することが求められますし、安定した職業生活の継続のためには、障害のある人が安心して生活できる地域作りも欠かせません。
障害者雇用を通じた働きやすい職場作り、障害のある人と企業の出会い、障害のある人への適切な情報と体験の提供、障害のある人が安心して生活できる地域作り、どれ一つとっても、一人の支援者や一つの支援機関だけできることではありません。
企業に対する支援だけでも、ハローワーク、障害者職業センター、障害者就業・生活支援センター、就労移行支援事業所など様々な機関の関わりが生じます。これらの機関がバラバラに企業を支援したのでは、効果的な支援は難しいでしょう。
障害のある人に対する支援では、就労支援機関だけでなく、生活支援や教育、医療などとの連携が求められますし、障害のある人が安心して生活できる地域作りでは、行政をはじめすべての関係者が市民も巻き込んで進めていくことが望まれます。
目の前の業務で忙しく悩んでいるからこそ、効果的・効率的な支援が求められているからこそ、ネットワークを意識した取組みが重要になりますが、宮就ネットではこのような地域ネットワークの形成を目指した活動を展開したいと考えます。
〇職業の「職」の視点
利用者をどう確保するか、登録者件数や就職件数をどう上げるか、業績評価をいかに達成するか、それによっていかに自分の評価を上げ、組織を維持・拡大するか・・・支援者や支援機関にとっては気になるところでしょう。 障害のある人や企業を数多く支援することは良いことですし、就職件数や定着率が上がり、支援費に関連する指標や業績評価の指標を達成することは望ましいことです。
しかし、例えば、就職しやすい対象者の確保に相当の労力を費やしたり、必要性の乏しい支援で件数を稼いだり、支援件数が増えるよう業務計上の仕方を工夫することに時間を費やすなど、必要以上に数値目標の達成に捕らわれてしまうと、何のための支援か分からなくなってしまうのではないでしょうか。こうなると、必ずしも「数値目標の達成」イコール「望ましい支援」とは言えないかもしれません。
教育学者の伊藤一雄は、職業は「職」と「業」の二語からなる合成語で、「業」は生業などの業(生きるためにどうしても逃げることのできない生活のための仕事)であるとする一方、「職」は職分(社会の一員として果たさなければならない役割)や天職(神によって与えられた才能を生かし神に身を捧げる)などの職であり、個人が全体に対して負わなければならない連帯的な意味を持つ仕事の総称だとしています。
組織を存続させるには、身過ぎ世過ぎとしての「業」は必要で、否定されるものではありませんが、普段の組織的なしがらみから少し離れて考えてみる・・・宮就ネット活動がそのような場になれればと思っています。
一般社団法人
宮城就業支援ネットワーク代表理事
相澤 欽一
設立経緯と
最近の主な活動
<設立経過>
2014(H26)年から2年連続で宮城県が障害者雇用率全国最下位になったことなどから宮城県内の障害者就業・生活支援センター(ナカポツ)と仙台市障害者就労支援センターが連名で宮就ネットの設立趣意書(就業支援の課題や問題点を共有し解決に向けた協議を行い、研修等を通じて人材育成に取り組むことなど)を宮城労働局、宮城県、仙台市に提出し、2016年(H28)に宮就ネットが設立されました。
2025(R7)年に、行政などの委託事業を受託し、県内の障害者雇用・就労支援を推進できるよう一般社団法人となりました。
<最近の主な活動>
- 2025. 4. 7
- 一般社団法人として登記
- 2025. 2.24
- 2025年度第二回宮就ネットセミナー「就労選択支援について学ぶ」
- 2024.12.11
- 宮城県雇用対策課との話合い(障害者雇用推進事業に対する提案)
- 2025. 5.31
- 2025年度第一回宮就ネットセミナー「定着支援のあり方を考える」&総会
- 2024. 5.30
- 宮城県雇用対策課・障害福祉課、仙台市との話合い(日本財団助成事業に係る打合せ)
- 2024. 3. 1
- 2023年度第二回宮就ネットセミナー「宮城の就業支援ネットワークを考えるⅡ」
- 2024. 1.23
- オンライングループワーク「企業支援におけるHWとナカポツや支援機関との連携Ⅲ」
- 2023.12.18
- 行政(労働局、県雇用対策課・障害福祉課、仙台市)との情報共有・意見交換会
- 2023.11.20
- 大阪市障がい者就業・生活支援センターの仕組みを学ぶオンライン研修会
「国のナカポツ事業と自治体の就労支援の事業を一体的に実施している大阪市の取組みを学ぶ」 - 2023.11. 9
- 精神障害者雇用推進セミナー仙台会場(ナカポツ部会担当:アデコと共催)
(11.14 大崎会場、11.16 石巻会場、11.20気仙沼会場) - 2023.10.12
- 企業支援との関わりで悩む支援者に対し企業8社が助言する支援者向け相談会
- 2023. 8.29
- オンライングループワーク「企業支援におけるHWとナカポツや支援機関との連携Ⅱ」
- 2023. 6.29
- オンライングループワーク「企業支援におけるHWとナカポツや支援機関との連携Ⅰ」
- 2023. 6. 7
- 2023年度第一回宮就ネットセミナー「宮城の就業支援ネットワークを考える」
- 2023. 3.17
- 行政(労働局、県雇用対策課、仙台市)との情報共有・意見交換会
- 2023. 1.26
- 2022年度第二回宮就ネットセミナー「企業が行う雇用管理の視点から就労支援を考える」
- 2022.11.14
- 仙台会場精神障害者雇用推進セミナー仙台会場(ナカポツ部会担当:労働局・県との共催)
(11.16 大崎会場、11.17 気仙沼場、11.18石巻会場) - 2022. 8.25
- 日本職業リハビリテーション学会宮城大会:実行委員会として3つの大会ワークショップを開催
オンデマンド配信(2022.8.25~9.11)、ライブ配信(2022.8.27~8.28)
大会ワークショップⅠ「就労⽀援と相談⽀援〜相談⽀援機関における就労相談のあり⽅〜」
大会ワークショップⅡ「みのりある職場実習のために〜企業の現状と⽀援者の役割〜」
大会ワークショップⅢ「安定した職業⽣活を継続するための⽀援〜地域⽣活⽀援の視点から〜」 - 2022. 6.30
- 2022年度第一回宮就ネットセミナー「福島就業支援ネットワークの活動から学ぶ」&総会